はじめに|会社を辞めたら何をしないといけないの?
のんびりしているあなたに…ちょっと待ってください!
退職後、自由な時間にホッとしていませんか?
実はその裏で「自分でやらないといけない重要な手続き」が静かにあなたを待ち構えています。
退職金の振り込みや、雇用保険(失業給付)など、“収入面”には意識が向いていても、
社会保険や年金などの“支出・手続き面”については、
「会社が手続きしてくれるのでは?」
「親切に教えてくれるだろう」
なんて思っていませんか?
……正直に言うと、私もそうでした。
しかし現実は、誰も事細かに教えてはくれません。
手続きを知らずに放置すると、損をしたり、手間が増えたりすることも。
この記事では、退職後に必要な3つの重要手続きを、体験談を交えてわかりやすく紹介します。
「やっておけばよかった」と後悔しないために、ぜひチェックしてください。
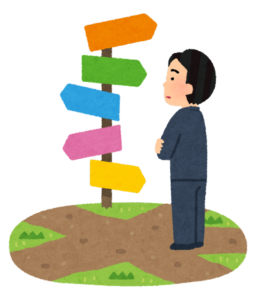
全体の流れ|3つの重要な手続きを把握しよう
早速ですが、退職後に行わなければならない手続きは以下の3つです。
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)から個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換
- 国民年金の資格変更
- 国民健康保険の加入手続き
この3つの手続きについて、場所と期限をまとめた表がこちらです。
| No. | 手続き | 手続きを行う場所 | 期限(目安) |
|---|---|---|---|
| 1 | iDeCoへの移換 | Web(証券会社など) | 退職から6ヶ月以内 |
| 2 | 国民年金の資格変更 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 3 | 国民健康保険の加入 | 市区町村役場 | 退職日の翌日から14日以内 |
【手続き①】iDeCoへの移換(企業型DCの取り扱い)
企業型DCをしていた方は要注意!
勤務先で企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入していた場合、退職後はそのまま運用が停止されるため、iDeCo(個人型確定拠出年金)への移換手続き が必要になります。
この移換をしないまま放置すると、資産は 自動的に「国民年金基金連合会」へ移換 されます。
自動移換されると以下のようなデメリットがあります。
- 資産が 強制的に現金化 される
- 運用が 完全に停止 される
- 管理手数料が 毎月差し引かれ続ける
- 掛金の拠出も不可能となるため 所得控除も受けられない
せっかく積み立てた資産を無駄にしないためにも、自分でiDeCoへの移換手続き を行いましょう。
iDeCo移換に必要なもの
手続きには、以下の情報が必要です。
- 基礎年金番号(年金手帳やマイナポータルで確認可)
- 記録関連運営管理機関(企業型DCの管理機関名。加入者証などで確認)
移換先の金融機関を選ぶ
iDeCoを始めるには、まず 金融機関を決める 必要があります。選べる金融機関の例としては、
- 楽天証券
- SBI証券
- マネックス証券 など
筆者は楽天証券でiDeCoへの移換を行いましたが、2回の申請失敗 を経て、完了までに5ヶ月かかりました…。
実際の移換でどんな失敗が起きるのか、対策も含めて以下の記事でまとめています👇

【手続き②】国民年金の資格変更
手続き期限に注意
退職日の翌日から数えて14日以内に、お住まいの市区町村役場で国民年金の資格変更手続きを行う必要があります。
もし退職後の忙しさなどで14日以内に手続きできなくても、後日手続きを行うことは可能です。ただし、そのまま放置していると「未納期間」が発生し、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性があります。
また、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響することがあるため、なるべく早めに手続きするのが安心です。
資格変更に必要なもの
手続きの際には、以下の書類を持参してください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職日が確認できる書類(退職証明書/健康保険資格喪失証明書/雇用保険被保険者離職票のいずれか1点)
- 本人確認書類(マイナンバーカード/運転免許証/健康保険証など)
免除制度や猶予制度もある
前年の所得が一定額以下の場合や、失業により経済的に困難な状況にある場合、申請して承認されると、保険料の免除や納付猶予の制度を利用できます。
免除制度では、本人に加えて配偶者や世帯主の所得も審査対象になります。一方、猶予制度では本人と配偶者のみが対象で、世帯主の所得は関係ありません。
| 制度名 | 対象年齢 | 審査対象 | 免除内容 |
|---|---|---|---|
| 保険料免除 | 20歳以上 | 本人・配偶者・世帯主の所得 | 全額〜4分の1の4段階免除 |
| 納付猶予 | 20歳〜49歳 | 本人・配偶者の所得(世帯主は対象外) | 全額猶予(後納可能) |
また、免除・猶予制度の所得基準は、以下の計算式が目安となります。
- 「扶養親族等の数+1」×35万円+32万円以下
- たとえば単身者の場合、納付猶予の目安は前年所得67万円以下となります。

【手続き③】国民健康保険の加入手続き
退職後の健康保険をどうするか決定
会社を退職すると、社会保険から自動的に脱退となります(健康保険証は会社に返却)。
そのため、退職後の健康保険をどうするか、以下のいずれかから選ぶ必要があります。
- 家族の社会保険の扶養に入る
- これまでの社会保険を任意継続(最長2年)
- 国民健康保険に加入
もし、社会保険に加入しているご家族がいる場合は、その扶養に入るのがもっとも負担が少なく済みます(保険料不要・手続き簡単)。
扶養に入れない場合は、「任意継続」か「国民健康保険」を選ぶことになります。
任意継続の主な特徴
- 扶養家族がいる場合もそのまま保険加入となる
- 付加給付などの独自の給付が継続利用可能
- 社会保険料控除の対象になる
- 保険料は在職中の約2倍になることが多い
- 加入できるのは最大2年間
- 保険料は2年間固定
- 出産手当金・傷病手当金は支給されない
これらの条件が合わない場合や、保険料の負担が重く感じる場合は、国民健康保険 の加入を検討します。
国民健康保険の加入について
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で加入手続きを行う必要があります。
14日を過ぎても手続き自体は可能ですが、保険料は 退職日にさかのぼって請求 されます。
さらに、手続きが遅れると 無保険期間 ができてしまい、その間に病院を受診した場合は、医療費が全額自己負担 になることもあります。
加入手続きに必要なもの
国民健康保険の加入手続きには、以下の書類が必要です。
- 退職を証明できる書類(退職証明書/健康保険資格喪失証明書/雇用保険被保険者離職票のいずれか)
- 本人確認書類(マイナンバーカード/運転免許証/健康保険証など)

退職後すぐにやっておくと良いこと・お金に関する注意点
退職すると毎日の生活リズムが変わるだけでなく、これまで会社に任せきりだったお金に関することも すべて自分で手続きする 必要があります。
「時間があるからゆっくりやればいい」と思っていると、支払いの通知や必要書類が届いて慌てる…なんてことも。
ここでは、退職後すぐに取りかかっておくと良いことや、意外と見落としがちな お金の注意点 についてまとめておきます。
離職票が届いたら失業給付の申請
退職後、数日〜数週間ほどで「離職票」が自宅に届きます。
これは失業給付(いわゆる失業保険)を受け取るための必要書類です。
失業給付の申請は、お住まいの地域のハローワークで行います。申請から最短7日間の待機期間を経て、一定の条件を満たすことで給付が開始されます。
会社都合退職か自己都合退職かによって給付開始時期や支給期間が異なるため、内容をよく確認しましょう。
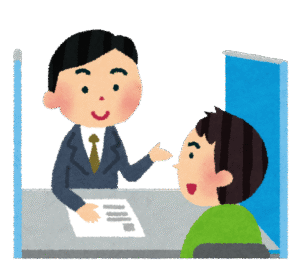
住民税の支払いは退職後も発生(普通徴収・特別徴収の違い)
会社に勤めている間は、住民税が給料から自動的に引かれていた方が多いと思います(これを「特別徴収」と言います)。
退職後はその仕組みがなくなるため、住民税は自分で支払う「普通徴収」に切り替わります。
これは自治体から送られてくる納付書に基づいて、年4回の分割払い で支払う形になります。
特に注意が必要なのが、退職月や翌月にまとめて一括で支払うケースもある こと。
退職前に住民税の徴収方法を確認して、必要であれば会社に「普通徴収でお願いします」と伝えておくのも手です。

健康保険や年金の支払い月はズレるため注意
退職後は、健康保険や年金の加入先が変わるだけでなく、請求が来るタイミングもバラバラになります。
例えば…
- 健康保険(国保)の納付書は、加入手続きをしてから数週間後に届く
- 国民年金の納付書は、申請から約1ヶ月後に送られてくる
- 住民税は前年度の所得に応じて、6月以降に請求が始まる
このように「退職してすぐ請求がくる」ものもあれば「しばらくしてから急に届く」ものもあります。
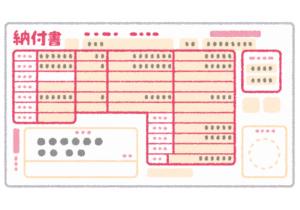
【体験談】私の場合はこうだった(任意継続しなかった理由など)
実際に手続きしたタイミング
今までご紹介してきた3つの手続きですが、私は退職後、期日内にすべてを完了することはできませんでした。
そもそもこの記事を書くキッカケとなったことが、まったく期日を知らず”のほほん”と過ごしていた戒めでもあります…
私の実際に行ったタイミングは以下の通りです。
- iDeCoへの移換: 退職日翌日から27日後
- 国民年金の資格変更: 退職日翌日から56日後
- 国民健康保険の加入手続き: 退職日翌日から56日後

トラブルや混乱があった点
iDeCoへの移換
退職前に調べていたこともあり、「移換には6ヶ月の猶予がある」と知っていました。そのため、退職後に少し落ち着いたタイミングで手続きを始めました。
ただ、手続きを進める中でいくつもの問題が発覚し、最終的に完了できたのは退職日から123日後(5ヶ月目)となってしまいました。
詳細なトラブルと対応については、こちらの記事をご参照ください。
国民年金と国民健康保険の手続き
退職後、市役所に届け出る意識がまったくなく、「会社がすべて手続きしてくれる」と思い込んでいました。そのため、長い間放置してしまっていたのです。
その後、iDeCoの手続きがうまく進まず、人に相談したところで「国民年金と国民健康保険の手続きが必要」と教えてもらい、ようやく必要書類を調べて役所へ向かいました。
幸いにも、
- 保険料は さかのぼって支払い可能
- 病院にかかるような病気をしていなかった
という点で、大きな問題にはなりませんでした。結果オーライとはいえ、運が良かっただけだとは思います。
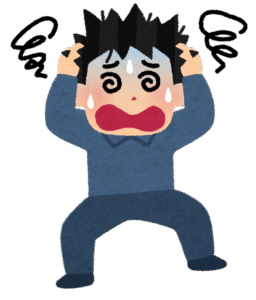
自分がどういう選択をしたかとその理由
iDeCoへの移換
私は2020年秋頃に、YouTubeの「両学長 リベラルアーツ大学」チャンネルに出会い、高配当株やつみたてNISAを始める中で、楽天証券での口座開設を行っていました。
その流れで、iDeCoも楽天証券に決めました。
国民健康保険の加入手続き
私は以下の理由から、任意継続ではなく国民健康保険を選びました。
- 被扶養者がいない
- 任意継続の保険料(在職時の約2倍)と、居住地の国民健康保険料を比較した結果、国保の方が安かった
- ここ数年、病院にほとんど行っていなかった
これらを踏まえ、「社会保険を継続するメリットを充分に享受できない」と判断したからです。
この選択が、将来的に後悔につながる可能性もありますが、現時点では納得しています。
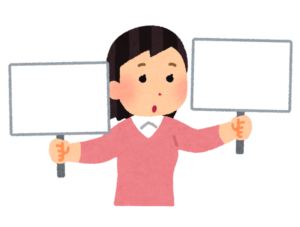
まとめ|「無職になったらすること」チェックリスト
退職後にやるべき3つの重要手続きは以下の通りです。
✅ 企業型DC → iDeCoへの移換(6ヶ月以内)
✅ 国民年金の資格変更(14日以内)
✅ 国民健康保険の加入(14日以内)
どれも期限があるため、のんびりしていると手遅れになることも。自分のライフプランを守るためにも、早めの対応を!

最後に|やらなければいけないことは意外と多い
退職後にやるべきことは、思っている以上に多くあります。
ですが、事前に「何をすればよいか」を把握しておけば、時間に余裕を持って比較検討ができ、慌てず落ち着いて対応できます。
私のようにトラブルを経験しないためにも、しっかり準備を整えて、必要な手続きを一つひとつ丁寧に進めていきましょう。

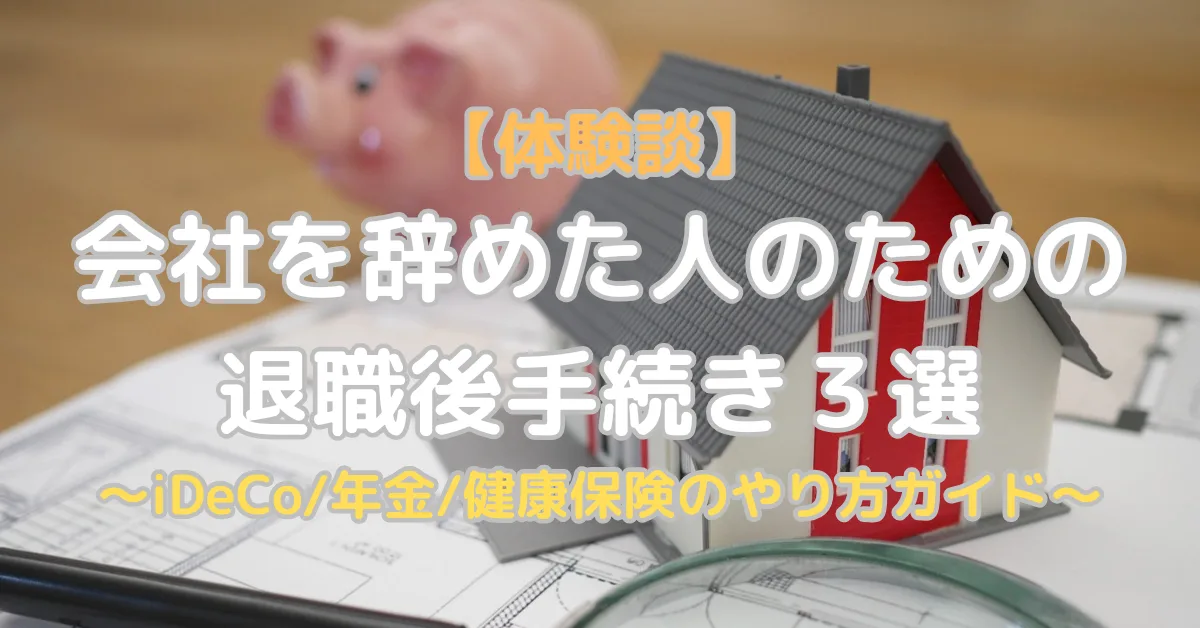


コメント