はじめに
2024年12月末、私は長年勤めた会社を退職しました。
勤めていた会社では、入社当初の「確定給付型企業年金(DB年金)」から、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」に途中で移行されました
移行された当時の私は投資の知識ゼロ。
正直、「投資=ギャンブルでお金が減るもの」と思い込んでいたため、企業型DCでは迷わず100%現金担保型を選んでいました。
ところがその数年後、YouTubeの「両学長 リベラルアーツ大学」チャンネルに出会ったことで考え方が変わります。
少しずつ投資を学び、「現金だけで守るより、インデックス投資を組み合わせた方が将来の可能性が広がる」と気づき、徐々に分散投資へ切り替えました。
そして退職を機に、企業型DCをiDeCo(個人型確定拠出年金)に移すことに。
今回は、確定拠出年金の受け取り方や注意点を、自分の体験を交えて解説します。

退職金受け取りと「退職控除」の選択
退職直前、会社から「退職金の振込先」と「退職控除を使うかどうか」の資料が届きました。
当時の私は深く考えず、「退職控除が使えるなら使わないと損!」と思い、迷わず控除使用を選択しました。
退職後、無事に退職金が口座に振り込まれましたが、ここで勘違いに気づきました。
- 退職金と企業型DCが合算され、退職所得控除が反映された金額が振り込まれる
- 振り込まれた企業型DCの金額を、別途iDeCoに移す
と私は思い込んでいたのです。
しかし、実際は企業型DCから直接iDeCoに移行することになるため、早期退職の時点では企業型DCに対して退職所得控除は適用されませんでした。

iDeCo受け取り時の税金の仕組み
「え、じゃあiDeCoに移したお金に税金がかかるの?」と焦りますよね。
私も最初はそう思いました。でも調べてみると、救済策や計算方法があることがわかりました。
退職所得控除の計算式は以下の通りです。
- 勤続年数20年以下:40万円 × 勤務年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
※ 勤務年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。
ここで大事なのは「iDeCoを受け取るタイミング」です。
- 退職金受け取りから5年以上経過した後にiDeCoを一括受け取り
→会社勤務期間ではなく、iDeCo加入期間(5年以上)で改めて計算された退職所得控除額が利用可能。 - 退職金受け取りから5年未満にiDeCoを一括受け取り
→会社勤務期間で計算された退職所得控除額から、すでに受け取った退職金分を差し引いた残額分が利用可能。
私の場合、退職所得控除の限度額を少し超える見込みのため、一部は課税される見込みです。

iDeCoは分割受け取りも可能
iDeCoは一括だけでなく、年金形式(分割)で受け取ることもできます。
分割なら雑所得として課税が分散され、安定した収入として取得できます。
ただし、毎回受取額に対して課税されることや、iDeCo口座に残額を預けたままになる点は少し気になるところ。
私は退職所得控除を使って一括で受け取り、自由に生活費や投資資金として使えるお金として確保する方向で考えています。

まとめ|あと4〜5年、情報を追いながら作戦を練る
iDeCoは受け取り方や受け取り時期によって税負担が大きく変わります。
私の場合は、法律改正で「5年ルール」が「10年ルール」に変わる過渡期にあたり、情報チェックは必須です。
iDeCo受け取りまでにはあと4〜5年残されている私ですが、その間に勉強を重ね、自分にとって最も納得できる方法を見つけたいと思っています。
ここまで読んでくれた方へ、早期退職を選択する場合の、私からのアドバイスです。
- iDeCoや退職金の受け取り方やタイミングは大事
・一括か分割かで税金の負担が変わります。
・退職後すぐに一括受け取りする場合は、退職所得控除の条件を確認しましょう。 - 企業型DCからiDeCoへの移行での控除適用の誤解に注意
・退職所得控除適用は退職金だけに適用される
・iDeCoの受け取り方や期間によっては、改めて退職金と合算されて退職所得控除適用となるか、別途課税となるか決まる。 - 法律や制度変更に注意
・今後「5年ルール」が「10年ルール」に変わります。
・施行時期や経過措置も確認して、最適な受け取りタイミングを検討しましょう。 - ライフプランに合わせて受け取り方を選ぶ
・一括で自由に運用するか、分割で安定収入を確保するか、自分の生活スタイルに合わせて考えることが大切です。
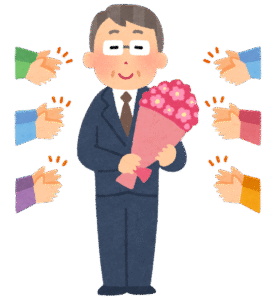

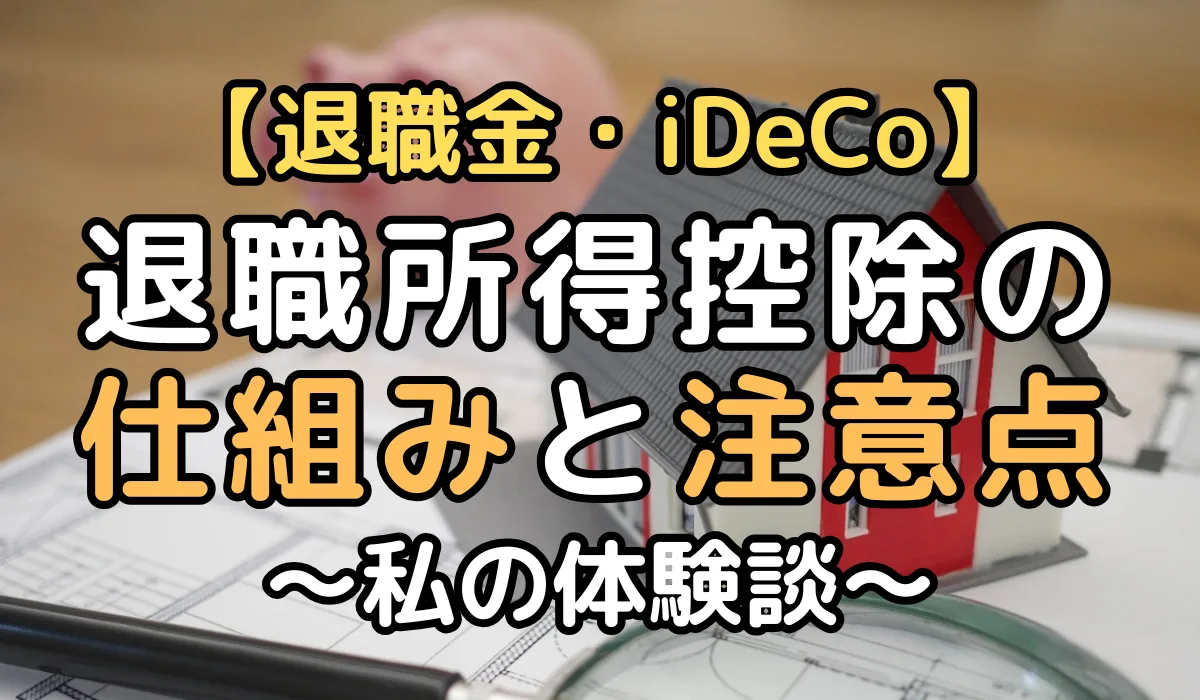
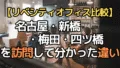
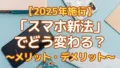
コメント