はじめに
私は長い間、「働いて稼ぐことがすべて」という意識で会社員生活を送ってきました。
毎月の給与明細の手取り額を眺めては「ああ、いつもの金額が振り込まれているな」と思い、将来についても「会社で働き続けて定年を迎えるのが当たり前」と考えていたのです。
しかし、心身のバランスを崩し休職を経験したことで、「このまま会社に依存して生きていくのは本当に大丈夫なのか」という不安が強くなりました。
再び職場に戻れたものの、働き方や収入に対する価値観は揺らぎ始めていました。
そんな時期に出会ったのが「株式投資」と「配当金」という考え方です。
自分の資産が働き、お金を生み出してくれる仕組みに触れたことで、仕事に対する見方が大きく変わりました。
この記事では、その変化を私自身の体験を通じてお伝えします。
同じように働き方や将来に悩んでいる方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。
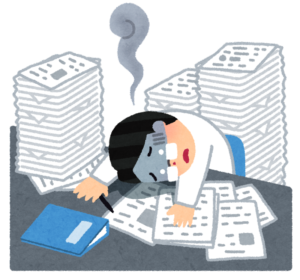
配当金に出会う前の働き方
配当金という存在を知る前の私は、ごく普通の会社員でした。
毎月の給料と年2回の賞与、それがすべての収入源であり、生活費も趣味の費用もすべてそこからやりくりしていました。
「お金を得る=会社で働くこと」という思い込みが強く、働くことに疑問を抱くこともほとんどありませんでした。
愚痴をこぼすことはあっても、「みんな同じだから仕方ない」と自分に言い聞かせるようにしていたのです。
ただ、現実は厳しいもので、昇格の候補に選ばれることもなく、年齢だけが上がっていく中で「自分は認められていないのかもしれない」と感じることもしばしば。
それでも目の前の仕事にしがみつき、次々と現れる業務に日々追われていました。
さらに心身のバランスを崩し、休職を余儀なくされたとき、(傷病手当を受け取れる期間が過ぎれば)「自分が働けなくなったら収入はゼロになる」という現実を突きつけられました。
復職してからも「また体を壊したらどうなるのか」という恐怖は拭えず、心のどこかで不安を抱えながら働き続けていたのです。

両学長チャンネルとの出会い
そんな不安を抱えながら復職したある日、会社の友人が何気なくこう言いました。
「YouTubeのリョウさんがさ〜」
私は最初、「こち亀の両さんかな?」をイメージしてしまい、会話がまったく噛み合いませんでした…(^^;
けれども詳しく聞いてみると、それは「リベラルアーツ大学」の両学長チャンネルのことでした。
試しに動画を見てみると、そこには今まで知らなかったお金の知識がわかりやすく語られていました。
貯金の方法、固定費の見直し、副業のすすめ、そして投資の基本…。
どの話題も、当時の自分がモヤモヤしていた将来の不安に直結する内容ばかりで、一気に引き込まれました。
それまで「働くこと=生きること」と信じて疑わなかった私にとって、両学長の「お金にも働いてもらおう」という考え方は目からウロコでした。
動画を見進めるうちに、会社以外から収入を得る道を具体的にイメージできるようになり、次第に「株式投資」という言葉が気になるようになっていきました。
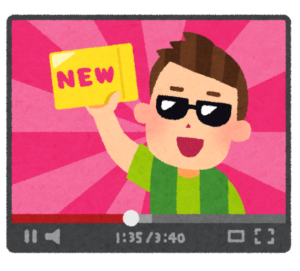
株式投資との出会い
正直に言えば、それまで私は株式投資にいいイメージを持っていませんでした。
「株=ギャンブル」「お金持ちがやること」「自分には縁がない」——そう思い込んでいたのです。
しかし、両学長チャンネルで語られる投資の話は、これまで抱いていたイメージとはまったく違いました。
長期・分散・積立という地道な方法であれば、投資は「ギャンブル」ではなく「資産形成の手段」になることを学びました。
最初の一歩として始めたのが「つみたてNISA」でのインデックス投資です。
証券口座を開設し、毎月一定額を自動的に投資信託に積み立てていく仕組みを設定しました。
「これなら自分でも続けられるかもしれない」と思えたのが大きかったです。
さらに勉強を進めるうちに、「高配当株投資」というスタイルにも興味を持ちました。
毎月コツコツと積み立てる投資が将来への備えなら、高配当株投資は「今の生活にプラスの現金をもたらしてくれる」もの。
目的の違いが自分にも腹落ちさせることができ、両方を並行して取り入れることにしました。
ただし、最初から大きな余裕資金があるわけではありません。
単元株(100株単位)で購入するには資金が足りず、当時はSBIネオモバイル証券(現在はSBI証券へ統合)を利用して1株単位からコツコツと買い始めました。
小さな一歩ではありましたが、「自分も投資家の一員になったんだ」と思えた瞬間は、今でも鮮明に覚えています。
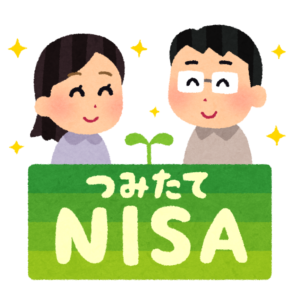
初めての配当金
投資を始めて数ヶ月後、ある日ふと証券口座を確認すると、そこには「配当金入金」という見慣れない文字が表示されていました。
金額は数百円程度で、外食一回分にも満たないくらいの小さな額でした。
それでも私にとっては大きな意味を持つ出来事でした。
会社からの給料以外に「自分が働かなくても得られたお金」を初めて実感した瞬間だったからです。
その小さな配当金で昼食代をまかなえたとき、「あ、これって確かに生活を助けてくれるんだ」と実感できました。
続けていけば、携帯電話料金、水道光熱費といった固定費の一部を配当金が肩代わりしてくれる未来も見えてきました。
給料だけに頼らず、少しずつでも収入の柱を増やせるという手応えは、金額以上に大きな安心感を与えてくれました。

配当金が与えた仕事観の変化
配当金を受け取るようになってから、私の「仕事」に対する捉え方は少しずつ変わっていきました。
以前は、生活のすべてを支えるのが会社からの給料だったため、
「仕事=人生の中心」
になっていました。
理不尽なことがあっても、昇進が望めなくても、「ここで稼ぎ続けなければ生きていけない」という思い込みから、目の前の仕事をただただこなし続けていたのです。
けれども、配当金という「第2の収入」が生まれたことで、気持ちに余裕ができました。
収入の100%を会社に依存しなくてもよいと気づいた瞬間、仕事を少し俯瞰した目線で見られるようになったのです。
そこからは、ただ「やらされる」働き方ではなく、
- 求められた最低限のクオリティは自分の責任として果たす
- 残りの時間で自分なりの付加価値をどう出せるか
- 作り出した時間で周囲の人やお客様にどんな手助けができるか
という主体的な意識に変わっていきました。
残業についても、以前は仕事が終わらないなど「必要に迫られて」対応していたのが、「何時までに終わらせるにはどこまでやるか」を考え、空いた時間で仲間に目を配るといった動きに変化しました。
結果として、定時退社がほとんどの日常になり、アフター5にリラックスしたり副業に挑戦したりする時間も生まれました。
もちろん、思いがけないトラブル対応や急な残業もゼロではありません。それでも「普段は自分でコントロールできる範囲がある」という実感は、心身のバランスにとって大きな支えとなりました。
私にとって配当金は、単なるお金以上の価値を持つ存在です。それは「働き方を変えるきっかけ」そのものでした。

自分の時間を取り戻す
定時で帰れるようになったことで、平日の夜に「自分の時間」がしっかり持てるようになりました。
これは私にとって大きな変化でした。
会社中心の働き方をしていた頃は、帰宅しても疲れ切っていて、ただ食事と風呂を済ませて寝るだけ。
休日も仕事のストレスから解放されず、リフレッシュできないまま次の週を迎えることが少なくありませんでした。
しかし、配当金のおかげで仕事を主体的に捉えられるようになり、残業も減った結果、毎日の生活にゆとりが生まれました。
平日の夜にリラックスしてバラエティ番組を観たり、資格取得の勉強に取り組んだり、副業にチャレンジする余裕も出てきたのです。
「自分の時間を自分でコントロールできる感覚」は、収入面での安心感と同じくらい大切なものでした。
働くことそのものは続けていても、「仕事=人生のすべて」ではなくなったことで、心の余裕と充実感を得られるようになったと感じています。
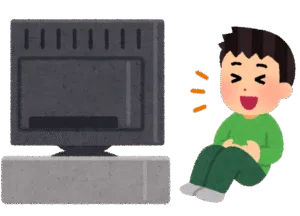
まとめ
配当金を得て感じた一番の変化は、「お金そのもの」よりも「心の余裕」でした。
働き方を根本から変えたわけではありません。それでも、会社以外から収入があるという小さな体験が、仕事との距離感を見直す大きなきっかけとなりました。
もし配当金がなかったら、今も「働かないと生活が成り立たない」という不安に押しつぶされ、受け身のまま働き続けていたかもしれません。
もちろん投資にはリスクが伴いますし、誰もが同じ成果を得られるとは限りません。けれども「給料以外に収入の柱を持つこと」が、これほどまでに精神的な安心感をもたらすとは想像もしていませんでした。
私にとって配当金は「将来の備え」であると同時に、「今を心穏やかに生きるための支え」です。
少しずつでも収入源を育てていけば、働き方や生き方をより主体的に選べるようになる――それこそが、配当金から学んだ最大の価値だと感じています。


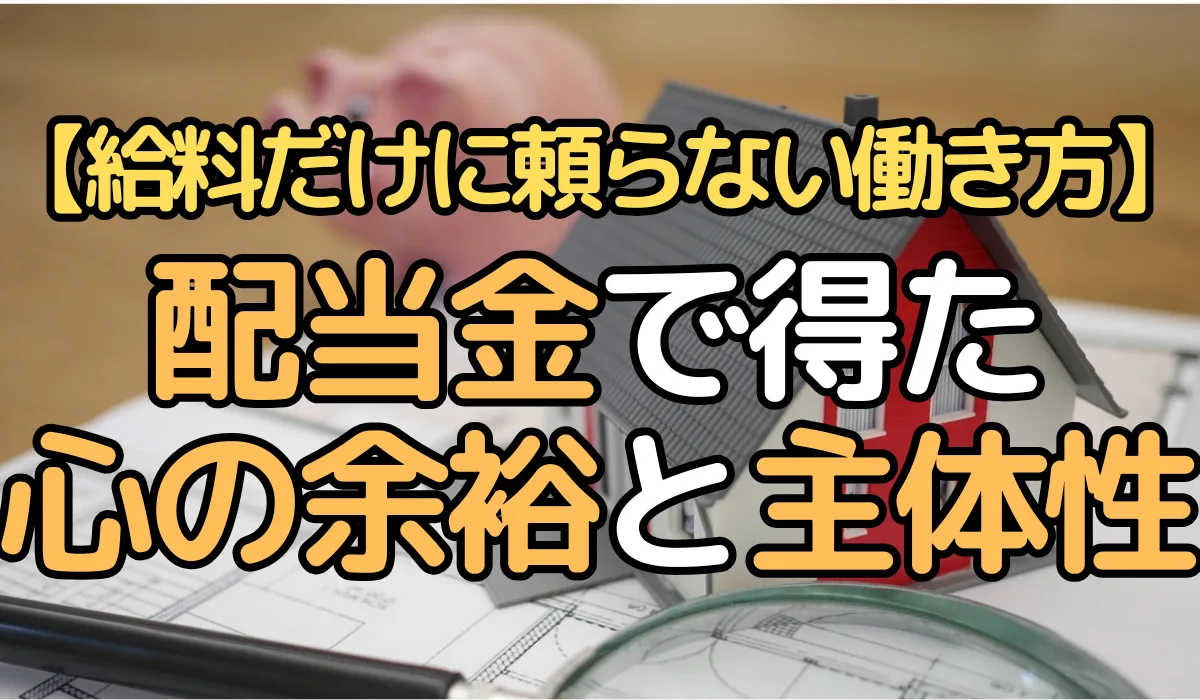
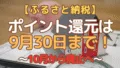
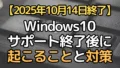
コメント