はじめに
「比べたくないけど、つい比べてしまう…」
そんな思い、誰しも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
「人と比べないことが大事」とよく聞くようになった今。
私も「他人は他人、自分は自分」と割り切れたら、どんなに楽だろうと思ったことが何度もあります。
けれど、SNSやオンラインのコミュニティを見ていると、
「ブログ開始1ヶ月で初収入!」「月100万円達成しました!」
そんなキラキラした投稿が次々に流れてきます。
もちろん、素直に「すごいな」と感じる部分もあります。
でもふと、こんな思いがよぎってしまうのです。
「それに比べて、自分は何をやってるんだろう…」
本当は、人と比べることで自分をすり減らしたくない。
でも、不安がまったくないわけでもない。
この記事では、そんな気持ちの揺れと向き合う中で、
私が少しずつ見つけてきた「3つの視点」をご紹介します。
- 「人と比べたくない」と思う理由
- それでも消えない「不安」との向き合い方
- 自分らしく生きるための“折り合いのつけ方”
どれも、特別な答えではありません。
けれど、「このままでいいのかな」と揺らぐ日々の中で、
私自身が等身大で感じた、ささやかな気づきです。
同じように感じたことがある方に、
そっと寄り添うような記事になれば嬉しいです。

行動のきっかけと背景
「会社を辞めたら自由になれる」と思っていたけれど
私が「会社を辞めても大丈夫かもしれない」と思えたのは、リベ大(リベラルアーツ大学)のYouTube動画と出会ったのがきっかけでした。
そこから貯金だけでなく、高配当株やインデックス投資を少しずつ学び、取り入れてみるように。
家計簿もつけ始め、収支額の数字と向き合うことで、これまで漠然としていた「お金の不安」が少しずつ輪郭を持つようになりました。
退職前には、資産のシミュレーションも何度も行いました。
60歳まで勤めた場合や、今すぐ辞めた場合。
年金の開始時期を早めた場合と遅らせた場合。
いくつかのケースを試してみた結果、「理論上は、このままでも100歳まで生活できる」と思えたことが、決断の後押しになりました。
ちょうどそのタイミングで、会社に「1年間出社せずに次のキャリアを探せる制度」があると知り、ありがたく活用させてもらうことに。
同時に、リベシティというオンラインコミュニティに入り、本格的に「お金・暮らし・働き方」について考える日々が始まりました。
それまで止まっていたブログも、ほんの少しずつですが再開。収益というほどのものではなかったけれど、それでも時折振り込まれる数百円に「自分にも何かできるかもしれない」と希望をもらっていました。
でも、リベシティの中には、ブログやYouTubeで大きく成果を出している方もたくさんいて──
「自分はまだ、全然うまくできていない…」
そんなふうに、思わず自分を下げて見てしまう気持ちが芽生えるようにもなっていきました。

① 「人と比べたくない」と思う理由
他人と比べて落ち込んだ経験、誰にでも一度はあるのではないでしょうか?
私も例外ではありません。
特に、SNSやコミュニティでの投稿を見ていると、自分よりもうまくやっている人、自信を持って発信している人がたくさん目に飛び込んできます。
「人は人、自分は自分」――それが正しいと、頭では分かっているつもりです。
実際、誰かと比べて上には上がいるし、下には下もいる。比べ始めたらキリがありません。
それでも私は、どこかで「自分も頑張っているのに…」という気持ちを持ってしまいます。
おそらく、自分でも気づかぬうちに、プライドが高い部分があるのでしょう…
だからこそ、他人の成果を見て素直に喜ぶどころか、焦りや劣等感に変わってしまうのです。
でも、そういう感情に振り回されないようにしようと、今は意識をするようにしています。
人と比べることをやめたとき、自分のペースで穏やかに生活できるようになりました。
「自分には自分のやり方がある」と思えるようになっただけで、日々の気持ちがずいぶん楽になります。
人と比べないことは、自分自身を守ること。
これは、私が退職して自由な時間を得てから、ようやく実感できるようになった気づきです。

② 「それでも不安」が消えないのはなぜか?
人と比べないことを意識し、自分のペースで生活できるようになった今。
それでも、ふとしたときに湧き上がってくるのが「このままで本当に大丈夫だろうか?」という不安です。
たとえば、仕事をしていないことで、社会の中で「誰かに必要とされる存在」でなくなってしまうんじゃないか…
そんな漠然とした喪失感のようなものを感じることがあります。
また、自由な生活は手に入ったけれど、だからこそ人とのつながりが薄れたり、孤立してしまうのではという不安も心のどこかにあります。
リベシティなどで人と交流する一方で、「あの人はあんなスキルがある」「自分には何もない」と感じてしまう瞬間も、正直まだあります。
さらに、お金に関しても、今は配当金や貯金でやりくりできていても、将来もしものことが起きたら?──
たとえば、親の介護が必要になったとき、自分自身の体が動かなくなったとき、突発的な出費が重なったとき…
そんな「想定外」があるかもしれないと考えると、安心しきることは難しいのが現実です。
不安の正体は、「目に見えない未来」への備えの無さなのかもしれません。
だからこそ、どこかで「もっとスキルがあったら…」「もっと稼げたら…」と考えてしまうのだと思います。
それは、慎重に生きようとする自分の優しさでもある。

③ 自分なりの折り合いのつけ方
どれだけ比べないように意識しても、不安が完全に消えるわけではありません。
だからこそ最近は、「不安をなくす」のではなく、「不安とうまく付き合う」方法を考えるようになりました。
退職後は、心と暮らしの整理を兼ねて、身の回りの物を少しずつ手放しています。
いわゆる “断捨離” のようなことですが、それは単に物を減らすだけではなく、
「今の自分にとって、本当に必要なものは何か?」を見直す作業でもありました。
SNSやリベシティに関しても、情報に触れることで刺激や学びを得られる一方で、
比較して落ち込んでしまうなら、見る時間を区切ったり、距離の取り方を日々工夫したりしています。
完全に離れてしまうと、今度は何もしなくなってしまう。
だから、自分にとって “ちょうどいい関わり方” を模索中です。
そして、過去の自分の行動や記録を見返すことも、最近は意識するようになりました。
「このとき自分はこう考えて、こう動いた」という実績が、自信や次の行動のヒントになります。
同じような場面に直面したとき、「あのときの自分はこうだったな」と立ち返ることができると、
落ち着いて判断できるようになるのです。
でも、自分にとって “安心できるペース” を知っておくことで、気持ちは少し楽になれる。
“自分なりの折り合い” は、すぐに答えが出るものではないかもしれません。
でも、不安を抱えながらも日々を積み重ねることで、少しずつ輪郭が見えてくるのだと感じています。
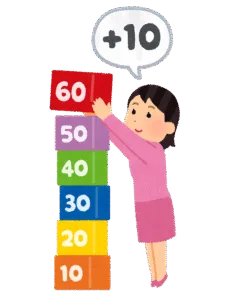
自分を責めない。短所を言い換えてみる
落ち込んでしまうとき、真っ先に浮かぶのは「自分ってだめだな…」という言葉かもしれません。
何かに挑戦してもうまくいかない、思うように成果が出ない、他人と比べて見劣りする──
そんなとき、つい自分の欠点や足りなさばかりに目が向いてしまい、勝手に落ち込んでしまう。
でも、「短所」と思っている部分も、見方を変えれば「自分らしさ」や「長所の裏返し」になることがある、と最近気づきました。
たとえば──
- 慎重すぎる → 失敗を防ぐために事前に丁寧に準備ができる
- のんびりしている → 周囲に安心感を与えるペースを持っている
- 人と比べて落ち込みやすい → 他人をよく見ていて、向上心がある証拠
- 不安になりやすい → 将来を真剣に考えているからこそ
こうして言葉を少し言い換えてみるだけで、気持ちが軽くなることがあります。
「この性格だからこそ、自分にはこんな良さがある」と、自分の一部を少しだけ肯定できる気がするのです。
それが、自分と仲良く付き合う第一歩かもしれません。
完璧な人なんていないからこそ、他人の長所と自分の短所を比べて自信をなくす必要はないと考えます。
自分の中の「嫌なところ」も、自分を構成している大事な一部。
だからこそ、その部分を無理に消すのではなく、「どう受け止めるか」「どう使っていくか」を工夫することが大切なのだと思います。

おわりに
「比べてしまうことが悪いわけではない」
「人と比べたくない」と思っていても、ふと目に入った情報に心が揺れてしまうことはあります。
「このままでいいのかな」と感じてしまうのは、決して弱さではなく、真面目に考えている証拠なのかもしれません。
私自身、会社を辞めて、自由な時間と経済的な土台が少しできたことで、ようやく「人と比べず、自分のペースで生きてみよう」と思えるようになってきました。
それでも、時にはSNSやオンラインコミュニティの情報を見て不安になったり、自分の立ち位置にモヤモヤしたりする日もあります。
でも、そんなときこそ思い出したいのは、「不安を感じる自分も、比べて落ち込む自分も、それを含めて自分なんだ」ということ。
比べないことを目標にしすぎて、それがまたプレッシャーになってしまっては本末転倒です。
その願いは、“人と比べてしまう自分” を否定せずに、ゆるやかに寄り添うことから始まるのかもしれません。
不安があるからこそ、丁寧に生きようとする。
誰かと比べて落ち込むからこそ、「じゃあ自分はどうしたいのか」を見つめ直せる。
そうやって少しずつ、自分にとっての「ちょうどいい暮らし方」が見えてくるのだと思います。
この記事が、同じような気持ちを抱える誰かの心に、そっと寄り添うものであったら嬉しいです。
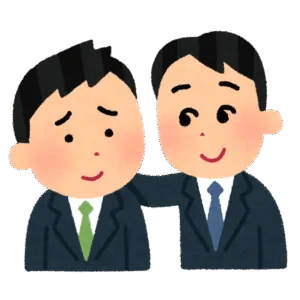

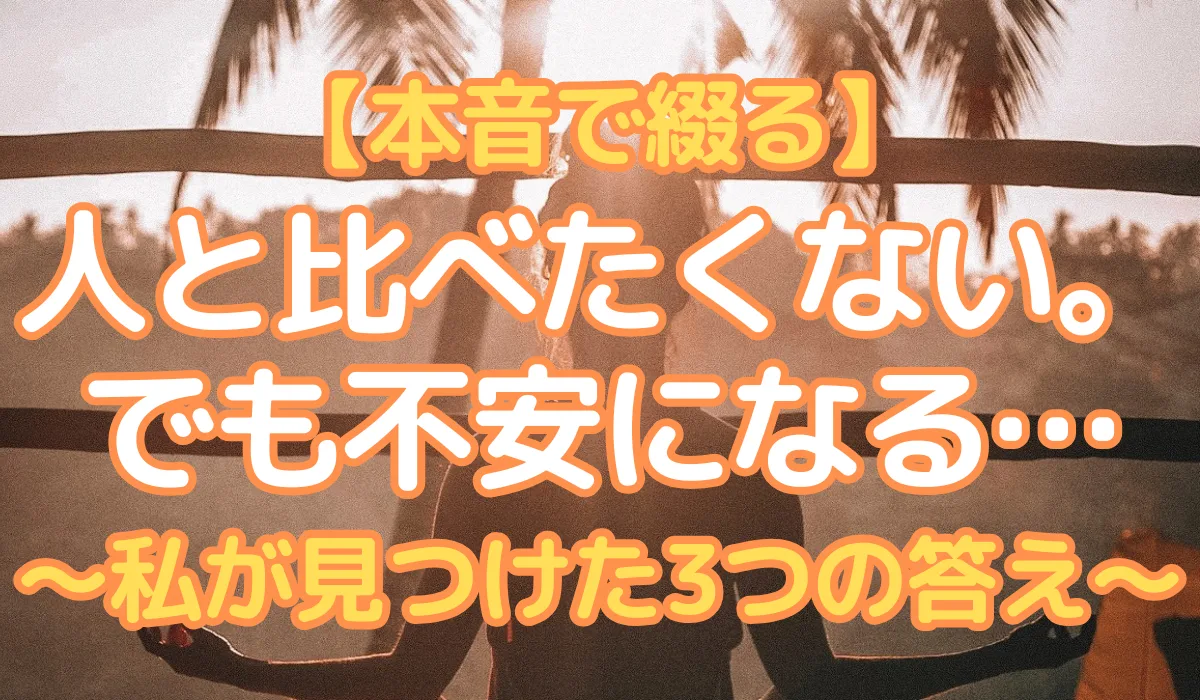
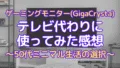
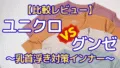
コメント