はじめに
私が子どもの頃、父親を見ていて「何でもできるんだなぁ」と思って見ていました。
DIY、自転車のパンク修理、屋根のアンテナ工事まで――黙々と作業をこなすその姿は、私にとって憧れそのものでした。
その影響もあり、社会人になりたての頃の私は「一人で何でも完結できる人材になりたい」と強く思っていました。
知識も技術もすべて身につけて、誰かに頼らずに仕事をやり遂げる――そんな理想像を描いていたのです。

理想と現実のギャップ
けれど、現実はそこまでうまくはいきませんでした。
仕事を進めるうちに、自分の知識や技術の浅さを痛感し、落ち込むことも多くありました。
それでも、「一人で何でもできるようになりたい」という思いを手放すことができず、がむしゃらに仕事に向き合っていました。
会社員生活の前半では、2年ほど勤めた部署から畑違いの新たな部署に移り、複数のお客様を対象とした仕事を長く続ける中で、少しずつ知識や技術を積み上げていく楽しさを感じていました。
ところが後半になると、同業種の部署ではあるものの異動が続き、人間関係にも悩みが増え、出世もうまくいかず、ついには休職も経験しました。
努力だけでは乗り越えられない壁があることを痛感しました。

「何でもできる人」への憧れの正体
今、会社を離れて冷静に振り返ると、
「一人で何でもできるようになる」
という目標は、どこか憧れや理想のままで終わる考え方だったと感じます。
会社には、さまざまな専門分野を持つ人がいて、どんな場面でも「自分よりすごい人」がいました。
自分が自信を持っていた知識でも、それを軽く上回る人がいる。
自分にはない「人をまとめる力」を持つ人がいる。
お客様の前で堂々と話す姿に圧倒されることもありました。
つまり、会社という場では「一人で完結する」ことよりも、
「互いに補い合って成果を出す」ことのほうが大切だったのだと思います。

頼ることは、弱さではない
自分の得意・不得意を正しく理解し、苦手なことは他人に頼り、得意なことで貢献する――
それが、チームや会社としての成果につながるのだと、今では素直に思えます。
当時の私は、「他人に頼る=弱さ」だと考えていました。
でも、実際には頼ることも大切な力のひとつです。
「苦手を無理に克服するより、得意を伸ばす」
「人を頼ることで、自分も他人も活かされる」
そう考えられるようになってから、ずいぶん心が軽くなりました。
この考え方が強まるにつれて、プロジェクトではできる限り自分がフォローに回り、他人の不足を埋めようと努力するようになりました。
それが、自分の存在価値だと感じられるようになったからです。

これからの学び方
それでも、知ること・学ぶことをやめたいわけではありません。
むしろ、広く浅くでも知識を得ながら、興味のある分野は深く掘り下げていく。
そうやって「得意」と「興味のあること」を少しずつ増やしていくことが、私にとっての “生涯学習” なのだと思います。
一人でなんでもできるようになることは難しくても、一人で “学び続ける姿勢” は持ち続けたい。
それが、今の私なりの答えです。
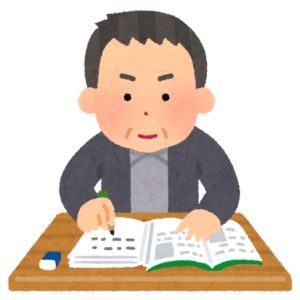
おわりに
子どもの頃に見た父親の姿を、今もときどき思い返します。
何でも一人でできる人に見えていたけれど、もしかしたら父親も周囲に支えられていたのかもしれません。
「一人で何でも」は、理想として持っていてもいい。
けれど、現実には人に頼りながら進んでいくのが自然な形なのだと思います。
完璧を目指すより、助け合いながら(みんなで)成長していく。
それが、私の今の「心に余裕のある生活」につながっています。


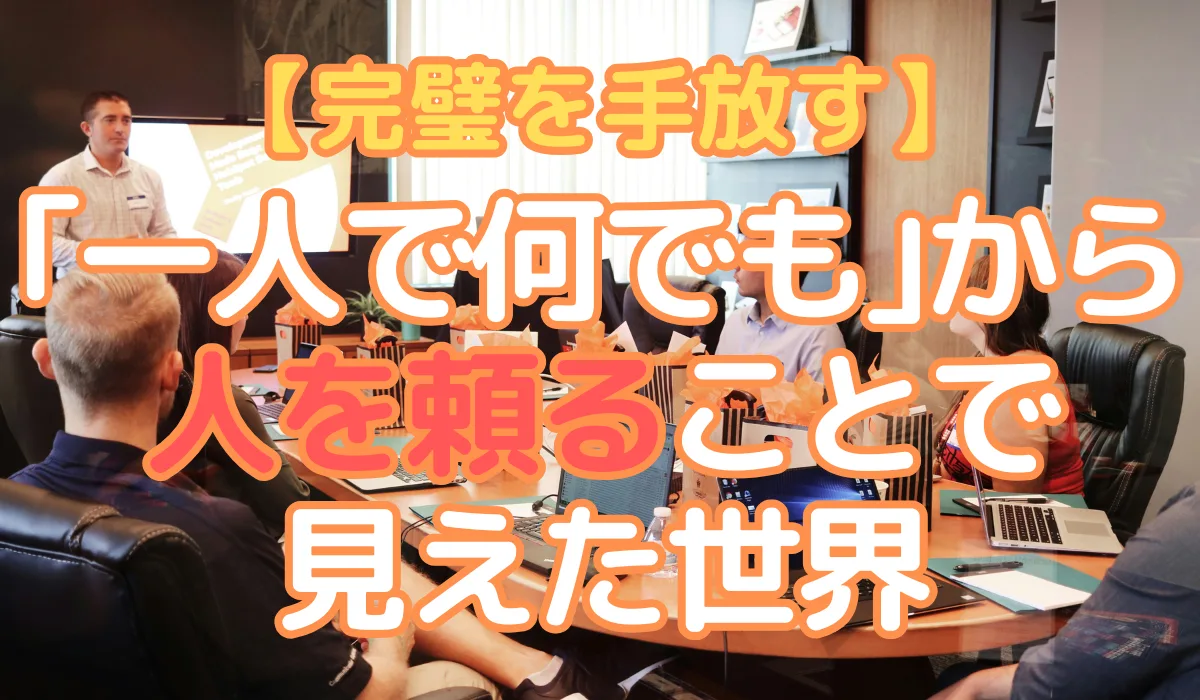
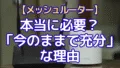
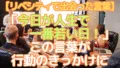
コメント