はじめに
最近、高市早苗議員が自民党総裁となった際に、
「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります。」
と発言され、その内容がニュースなどで大きく取り上げられました。
この言葉をきっかけに、ネット上でも「働くことの価値」や「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」について、さまざまな意見が交わされました。
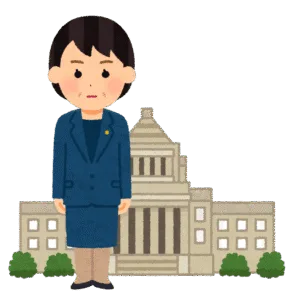
「ワーク・ライフ・バランス」とは何か
改めて「ワーク・ライフ・バランス」とは何かを調べてみると、「仕事」と「仕事以外の生活」を両立・調和させ、やりがいや満足感、充実感を得られるようにする考え方であり、日本では「仕事と生活の調和」とも表現されます。
ここ十数年で、働き方改革の一環としてよく聞かれるようになった言葉ですが、実際にはその “バランス” の取り方は人それぞれです。
過労によって身体や心を壊してしまった方、あるいは大切な家族を失った方からすれば、「ワーク・ライフ・バランス」を最優先に考えるのは当然のこと。
命や健康よりも優先すべき仕事など存在しない——そう痛感させられる出来事が、現実にいくつもあります。
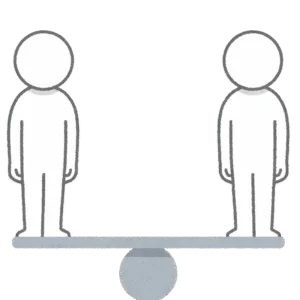
とはいえ「ワーク」に全振りせざるを得ない時期もある
一方で、人生のすべてのタイミングで完璧なバランスを取ることは、現実的には難しいとも感じます。
納期が迫っている、トラブル対応に追われている、誰かのミスをカバーしている——そんな場面では、「ワーク・ライフ・バランス」という理想を掲げても、逃げられない現実があるでしょう。
今の生活がすでに充実している人は「ライフ」を重視するのは間違いないでしょう。
でも、現状を変えたい、将来に向けて努力したい、仕事が楽しくてもっと深く知りたい——そんな “熱量を持った人” に、「バランスを取りなさい」と言っても、きっと響かないのではないかと考えます。
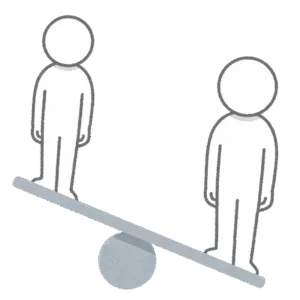
「多様性」との関係
最近ではネット上で強い意見を発信する人も増え、「多様性」という言葉もよく見かけます。
ただ、本来の「多様性」とは、さまざまな考え方や生き方を認め合うこと。
自分の意見を絶対視し、反対する人を否定してしまった時点で、その「多様性」の理念から外れてしまうのではないか——そんなことを感じます。
日本人は一般的に協調性や同調圧力が強いと言われます。
それは良くも悪くも「空気を読む」文化の結果なのかもしれません。
だからこそ、周りに合わせすぎて心や身体を壊してしまう前に、自分の悲鳴を聞き取る力、そしてそれを他人に伝える勇気が大切だと思います。

声を上げることの大切さ
私自身も会社員時代、一度心を病み、どうしても出社できなくなったことがありました。
「迷惑をかけてしまう」と感じつつも、勇気を振り絞って「声を上げる」ことができ、結果として休職制度を利用し、復職することができました。
あのとき、もし声を上げられなかったら、今の自分はいなかったかもしれません。
ただ、性格や正義感、立場などによって「声を上げる」ことが難しい人も多くいます。
だからこそ、声を上げることが “特別な勇気” ではなく、「報告」をするように自然に伝えることができる社会や職場が理想だと思います。
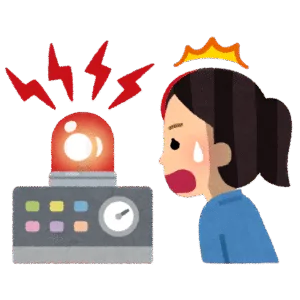
一生を通したバランスという視点
個人的な結論としては、もし誰もが一律にのんびり過ごせる社会であれば「ライフ」を優先するのが一番だと思います。
しかし現実には、子どもの頃の受験、資格取得、仕事を覚える時期、収入を増やしたい時期など、人生の中でどうしても「ワーク」を頑張らざるを得ない場面が訪れます。
だからこそ、「今この瞬間のワーク・ライフ・バランス」よりも、
一生を通して見たときにバランスが取れているかどうか が大切だと感じます。
働く時期があってもいい、休む時期があってもいい。
その両方が人生の中で自然に循環している——それこそが本当の意味での「ワーク・ライフ・バランス」なのかもしれないと考えます。
あなたは、今の自分の「ワーク・ライフ・バランス」に満足していますか?
それとも、これから少しずつ変えていきたいと感じているでしょうか。
人それぞれの答えがあっていい——そんな社会でありたいしあってほしいと思います。


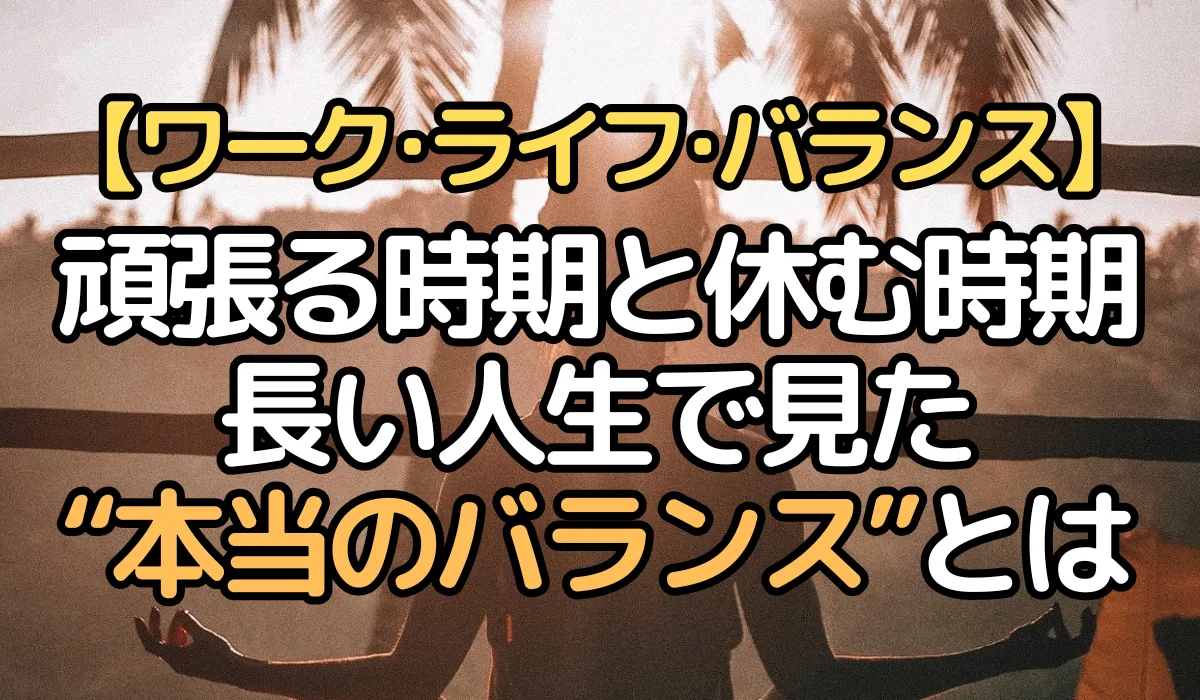
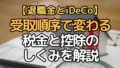
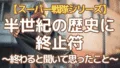
コメント