本記事の初版では「2024年分の確定申告で配当所得を分離課税にした場合でも、証券会社経由で自治体に情報が伝わり、住民税・国民健康保険料の課税所得に自動加算される」と記載していましたが、これは正確ではありませんでした。
実際には私のケースでは、分離課税とした配当所得は課税所得に加算されず、確定申告書で申告した課税所得がそのまま住民税・国保の算定に用いられていました。
読者の皆さまに誤解を与えたことをお詫びし、以下本文を修正しました。
はじめに
「配当金は20.315%の税率が源泉徴収されているから、もう申告の必要はない」と思っていませんか?
あるいは、「申告しなければ自治体にもバレないはず」と考えていた方もいるかもしれません (^^; 。
しかし、2023年以降は、証券会社が提出する「年間取引報告書」を通じて配当金の情報は国税庁→自治体へ共有される仕組みが強化されました。
ただし、配当を「申告分離課税」として確定申告した場合、その分が課税所得に自動的に上乗せされるわけではなく、確定申告書に記載した課税所得がそのまま住民税・国保料の算定基礎に使われることを確認しました。
つまり、自治体は配当の存在自体を把握していますが、「どの課税方式を選んだか」によって住民税・国保への反映のされ方が変わります。
知らずに過ぎると、住民税や国民健康保険料、配偶者の扶養条件などで不利益を受けることも。
この記事では、
- なぜ配当情報が自治体に伝わるのか?
- 申告方法によって何が違ってくるのか?
- 今後どう選択すべきなのか?
を、実体験を交えて解説していきます。

証券会社から自治体に配当情報が伝わる仕組み
2023年から、税と社会保障の連携がさらに強化され、金融機関(証券会社)が提出する「年間取引報告書」の内容が、国税庁を経由して地方自治体にも共有されるようになりました。
この年間取引報告書には、あなたが1年間に受け取った配当金の金額や支払元、源泉徴収額などが詳細に記載されています。
つまり、「申告不要を選んだから配当は住民税に反映されないはず」と思っていても、実際には
- 自治体はあなたの配当額を把握済み
- その情報を基に住民税や国保料を計算している
というのが現実です。
この背景には、マイナンバー制度の活用や所得情報の透明化が進んでいるという流れがあります。
そのため、「税務署に申告していない=自治体にも届かない」という従来のイメージは、すでに過去のものになりつつあります。
なお、証券会社が提出する情報は、以下のようなフローで自治体に届きます。
- 証券会社が「年間取引報告書」を税務署に提出(e-Tax経由)
- 国税庁が情報を整理・共有
- 自治体が税計算や住民サービス(保険料・扶養・非課税判定等)に利用
この流れは、納税者が申告するかどうかに関係なく進むため、自分で申告しないことが思わぬ影響を受ける時代になったともいえます。

総合課税 vs 分離課税 どちらがお得?
配当金の確定申告では、原則として以下の3つの課税方法を選ぶことができます。
- 申告不要(源泉徴収のみ)
- 分離課税(所得に含めず、別枠で20.315%)
- 総合課税(所得に含めて累進課税+配当控除)
このうち、「2. 分離課税」と「3. 総合課税」のどちらを選ぶかは、所得の額や扶養状況、国保料の計算、住民税の非課税判定など、複数の制度に影響するため、よく検討する必要があります。
💡 総合課税のメリット・デメリット
【メリット】
- 配当控除(最大10%)が受けられる:所得税+住民税で実質的な税負担が下がる可能性
- 住民税の均等割・非課税判定の対象所得が下がる(自治体によっては)
- 社会保険料控除や基礎控除等を活かしやすい
【デメリット】
-
所得税・住民税が累進課税(最大45%+10%)になるため、所得が高いと逆に重税に
💡 分離課税のメリット・デメリット
【メリット】
- 20.315%で税率が固定されるため、所得が高くても追加課税なし
- 所得に含まれないため、扶養に入れる条件(38万円以下など)を維持しやすい
【デメリット】
- 配当控除が使えないため、実効税率は下がらない
-
住民税・国保の計算にどう反映されるかは、課税方式の選択と自治体の運用による(「分離課税だから必ず加算される」というわけではない)
📌 では、どちらを選ぶべき?
| 状況 | 向いている課税方法 |
|---|---|
| 所得が低い・非課税世帯に近い | 総合課税(配当控除が効果的) |
| 所得が高い(課税所得900万円超など) | 分離課税(累進課税を避ける) |
| 配偶者の扶養に入りたい | 分離課税(所得に含まれない) |
| 国保料や住民税非課税を狙いたい | 総合課税 or 戦略的申告が必要 |
特に重要なのは、自治体には申告しなくても情報が届く(届いてしまう)こと。
つまり、分離課税にしても「住民税や国保料の計算には影響する」という点は、制度の落とし穴です。
たとえば私自身、2024年分は「分離課税で申告書に書かない=自治体には配当所得は伝わらない」と思っていましたが、
このことを知っていれば、「配当控除を活かして総合課税で出す」という選択もあったかもしれません。
🎯 結論:どちらが得かは「税だけ」では決まらない
確定申告では、所得税だけでなく、
- 住民税
- 国民健康保険料
- 配偶者(扶養)控除
- 住民税非課税・医療費助成の判定
など、複数の制度に影響することを考える必要があります。
「源泉徴収だけで終わっているから大丈夫」
「税務署に申告していないから自治体も知らない」
は、もう通用しません。
申告方法を選ぶ際は、「トータルでいくら得か?」を冷静にシミュレーションしてみることをおすすめします。
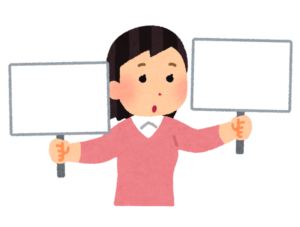
実際にやってしまった体験談(筆者の場合)
配当金に関する課税方法を選ぶ際、私は「今年はこの方法が有利だろう」とその都度考えて選んできました。
しかし、思い込みや制度への理解不足から、思わぬ落とし穴にはまってしまった経験があります。
私自身、2023年分の確定申告では、配当控除を受けるために総合課税を選択していました。
ところが、2024年分では退職により収入が大きく減る見込みだったため、住民税を抑える目的で配当所得を申告しない「申告不要制度(源泉徴収あり・分離課税扱い)」を選びました。
(※私は「特定口座・源泉徴収あり」を選択しています。)
当時は、「証券会社から自治体には情報は行かないだろう」と思い込んでいたのです。
しかし――。
2025年6月に届いた住民税の通知書を見て、配当所得がしっかり含まれた金額で課税されていることが判明。
「申告していないのに、なぜ!?」という驚きがあり、その後個人的に調べて「これは事前に知っておくべきだった…」という悔しさが残り、次に活かしたいと思いました。
同じように「申告しなければ自治体には伝わらない」と考えている人がいたら、ぜひ私のこの体験を通して、制度の仕組みを一度立ち止まって確認してみてほしいと思います。

今後どうする? 賢い選択のヒント
今後、配当所得がある人は以下のポイントを押さえておきましょう。
📊 配当金の課税方法 早見表(2025年版)
| 判断ポイント | 総合課税が有利なケース | 分離課税が有利なケース |
|---|---|---|
| 所得金額 | 年間課税所得が330万円以下(税率10%以下) | 年間課税所得が695万円超(税率20%以上) |
| 配当控除の効果 | 大きい(10%控除で税負担が軽減) | 受けられない(税率は一律20.315%) |
| 国民健康保険料 | 高くなる可能性あり(所得に含まれる) | やや低めになる可能性(所得に含まれないが、自治体には情報が届く) |
| 扶養に入りたい | 不利(配当が所得に含まれる) | 有利(所得に含まれない) |
| 住民税の非課税判定 | 有利になることがある(控除込みで所得減) | 不利になりがち(配当情報が伝わるため) |
| 手間 | 配当控除など計算がやや複雑 | 簡単(所得に含めない) |
| どんな人におすすめ? | 所得が少ない人/非課税狙い/住民税を下げたい人 | 所得が多い人/扶養に入りたい人/手間を減らしたい人 |
📝 補足
- 総合課税の目安:課税所得が少ない人(年金生活者・非課税世帯など)に有利
- 分離課税の目安:高所得者・扶養条件の維持が重要な人に向いている
- 国保料・住民税・医療費助成などへの影響を含めて、1〜2年分のトータルでの負担をシミュレーションしてみるのがおすすめです。
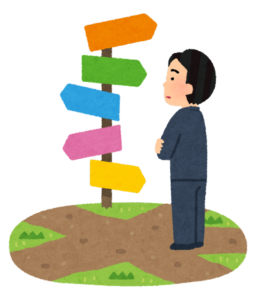
おわりに
配当金を受け取るようになると、「確定申告をするか、しないか」「総合課税か、分離課税か」など、選択肢が一気に増えます。
その中で「住民税」や「国民健康保険料」「扶養」など、税以外の制度にも影響を与えることは、意外と見落とされがちです。
私自身、実際に体験するまでは「確定申告しなければ自治体には伝わらないだろう」と思っていました。
ですが、
配当生活を目指す人にとって、「知らなかった」だけで住民税や国保料が大きく増えてしまうこともあります。
「損をしないために」「制度をうまく活かすために」、税制やそれに連動する制度について一度立ち止まって確認しておくことは、きっと将来の安心につながります。
この記事が、その一歩を踏み出すきっかけになればうれしく思います。

本記事は、筆者の体験と調査に基づく一般的な情報提供です。
住民税・国保料の算定方法や配当所得の扱いは自治体や申告方法によって異なる場合があります。
最終的な判断は必ず最新の制度や自治体窓口、税務署、税理士等の専門家にご確認ください。

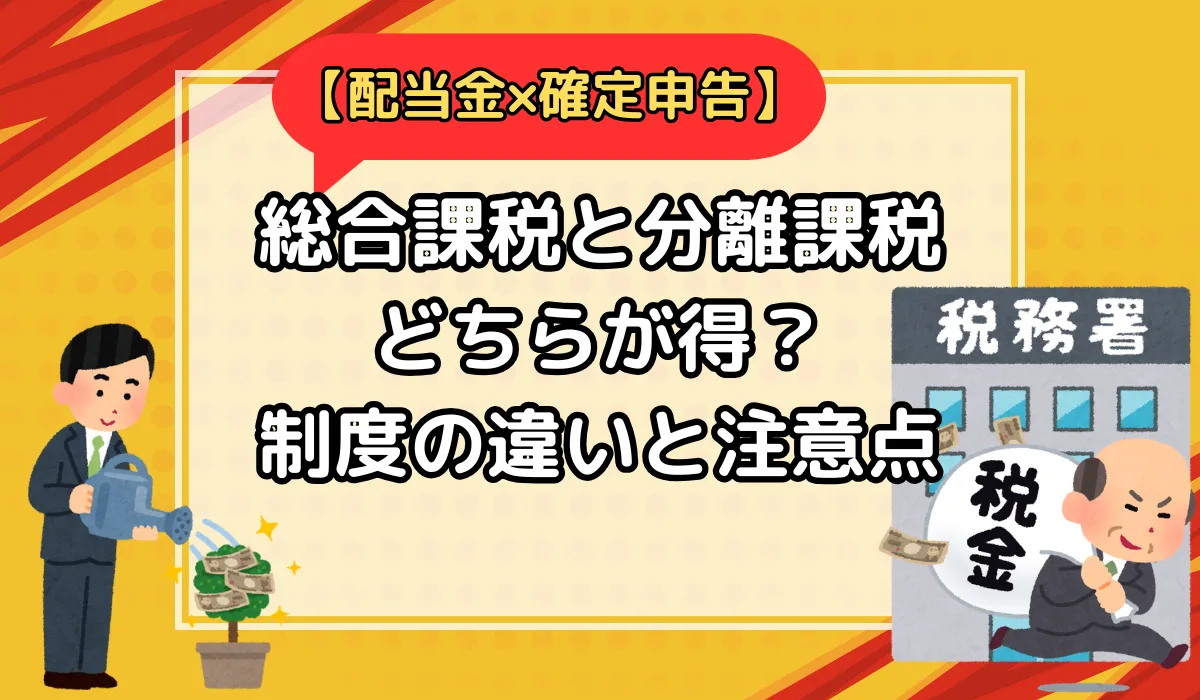

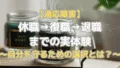
コメント