退職後も、ふるさと納税はできる?
会社を退職して収入がゼロになったら、ふるさと納税はできない——そう考えていませんか?
私もリーンFIREを始めた当初は同じ思い込みをしていました。
給与がゼロになれば住民税は非課税になり、寄付できる限度額もゼロになる――そう考えていたのです。
ましてや、高配当株の配当収入は証券会社が源泉徴収してくれているため、確定申告も不要。
「じゃあ、今年はふるさと納税はお休みだな」と早々に諦めていました。
しかし、あきらめムードで制度を調べてみると意外な事実が判明。
少額でも配当や副収入があれば、住民税はゼロにならず、ふるさと納税の対象になる場合があるのです。
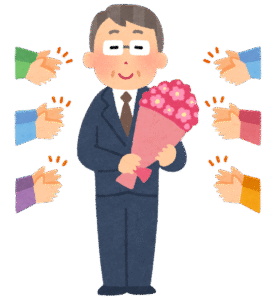
配当金と副収入で「非課税」にはならなかった
退職後の私の主な収入源は、高配当株の配当金です。
配当金は証券会社が源泉徴収を行ってくれるため、確定申告をしなければ自治体に直接報告されない――そう思い込んでいました。
そのため「収入ゼロ=住民税非課税世帯」だと勘違いしていたのです。
しかし実際には、証券会社と自治体の間で情報が共有されており、配当収入もしっかり住民税の計算対象になっていました。
さらに、ネット上で受けた単発の仕事からも月数千円ですが副収入があり、年間の総収入は非課税基準を超えていたのです。
国民健康保険料の減免申請を行った際に、収入明細を自治体へ提出したことで、その事実をはっきりと認識しました。
つまり、退職しても収入が完全にゼロでない限り、住民税は発生し、ふるさと納税の対象になる可能性があるということです。

◆ 配当収入が確定申告なしでも住民税の計算対象となることは、以下の記事に書いています。👇️
ふるさと納税とは(ざっくりおさらい)
- 今年の年収をもとに算出される「寄付限度額」の範囲内で、全国の自治体に寄付できる
- 寄付限度額までであれば、複数の自治体に寄付可能
- 実質負担は2,000円(それ以外は翌年の住民税から控除)
- 返礼品は寄付額の3割程度の価値
- ふるさと納税サイト(楽天市場やふるなび等)経由だとポイントももらえる(※2025年10月以降は廃止予定)

ふるさと納税の寄付限度額をシミュレーターで確認
住民税の非課税世帯にはならないことがわかり、「それならふるさと納税を活用しないと損だ」と考え始めました。
次に必要なのは、自分がいくらまで寄付できるのか=寄付限度額の確認です。
私は楽天ポイントをメインに使う「楽天経済圏」で生活しているため、楽天市場のWebページから、楽天ふるさと納税のマイページにある「かんたんシミュレーター」を利用しました。
国保料減免申請の際に自治体へ提出した年間収入額を入力し、寄付限度額を算出。
このシミュレーターでは、年収と家族構成などをもとに来年度の住民税から控除される上限額を簡単に確認できます。
実質負担2,000円で返礼品がもらえるうえ、寄付の範囲内であれば何度でも申し込めるのが魅力です。
私の場合、会社員時代より限度額は大きく減りましたが、ゼロではないことが分かった瞬間、選択肢が広がりました。

退職後は返礼品も変わった!私の選び方の変化
会社員だった頃のふるさと納税では、食品よりもガジェットや日用品をメインに選んでいました。
2020年にふるさと納税を知ってからは、長く使える実用品を重視し、ソーラーシートやランドリースタンド、シャワーヘッド、ホームカメラ、体組成計、簡易トイレ、充電池など、生活を便利にするアイテムを中心に寄付してきました。
しかし、昨年末に退職した今年は、寄付できる金額が大幅に減ってしまったことで、これまでのようにガジェットを中心に選ぶことが難しくなりました。
そこで、限られた寄付額の中で「使い切りやすい食品」も積極的に取り入れるようになったのです。
たとえば、今年は少額から選べるネギトロやカレーうどんといった食べ物を選びました。
消費しやすく、日々の生活に彩りを添えてくれる返礼品は、節約や健康維持の面でもメリットがあります。
また、楽天経済圏を活用している私の場合、楽天市場のふるさと納税ページにある「かんたんシミュレーター」を使い、年収をもとに寄付限度額を計算しました。
これにより、無理なく寄付できる金額を把握し、計画的に返礼品を選べるようになりました。
なお、ポイント還元の廃止が迫っていることもあり、今年は特に寄付のタイミングにも気を配っています。
2025年10月以降はポイント還元がなくなる見込みのため、返礼品だけが恩恵となりますが、2025年9月中までに寄付を済ませておけば、ポイントの二重取りが可能です。
こうした状況の変化を踏まえ、退職後のふるさと納税は、より節約や生活の質向上を意識した選択が求められるようになったと感じています。

ポイント還元が廃止される前に寄付を急ぐ理由
ふるさと納税は、寄付額に応じて返礼品がもらえるだけでなく、サイトによってはポイント還元まで受けられる「二重のメリット」が魅力でした。
私の場合は、楽天市場を経由して寄付を行っており、返礼品に加えて楽天ポイントも手に入るため、実質的な還元率はさらにアップしていました。
しかし、2025年10月以降は総務省の新しい方針により、このポイント還元が全面的に禁止される予定です(楽天グループは告示の無効確認を求めて提訴中ですが、現時点では廃止の見込みが高い状況)。
つまり、返礼品+ポイントというお得な組み合わせは、今年の2025年9月末までにしか体験できない可能性が高いのです。
この制度変更は、特に楽天経済圏で生活している人や、ポイントを家計の一部として活用している人にとって大きな影響があります。
返礼品だけでも充分魅力はありますが、せっかくなら「最後のポイント還元の恩恵」を受けられるうちに寄付を済ませるのが賢明です。

まとめ
退職後のリーンFIRE生活においても、ふるさと納税は節税や生活の質向上に活用できる有効な制度であることがわかりました。
退職前のような給与収入がなくなっても、配当金や副収入があれば、住民税の非課税世帯とはならず、寄付限度額が完全になくなるわけではありません。
むしろ、限られた寄付枠を上手に使い、実生活で役立つ返礼品を賢く選ぶことで、家計の助けにもなります。
また、2025年10月以降はふるさと納税のポイント還元が原則廃止される見込みであり、ポイントを活用した節約効果を得るためには、2025年9月末までの寄付が重要です。
このタイミングを逃さずに寄付を済ませることが、賢い選択と言えるでしょう。
会社員時代と比べて寄付できる金額は減るものの、食品や日用品など、無理なく消費できる返礼品を中心に選ぶことで、より実用的で満足度の高い活用が可能です。
限られた限度額の中で無駄なく使い切ることが、退職後の生活においては特に大切になります。
まずはご自身の寄付限度額をシミュレーターで確認し、生活に役立つ返礼品を探してみてください。
今年のポイント還元があるうちに動くことで、よりお得にふるさと納税を楽しめます。
この記事が、退職後のふるさと納税に関心のある方の参考になれば幸いです。

◆ ふるさと納税に関する過去記事もありますので、ぜひご覧ください。👇️

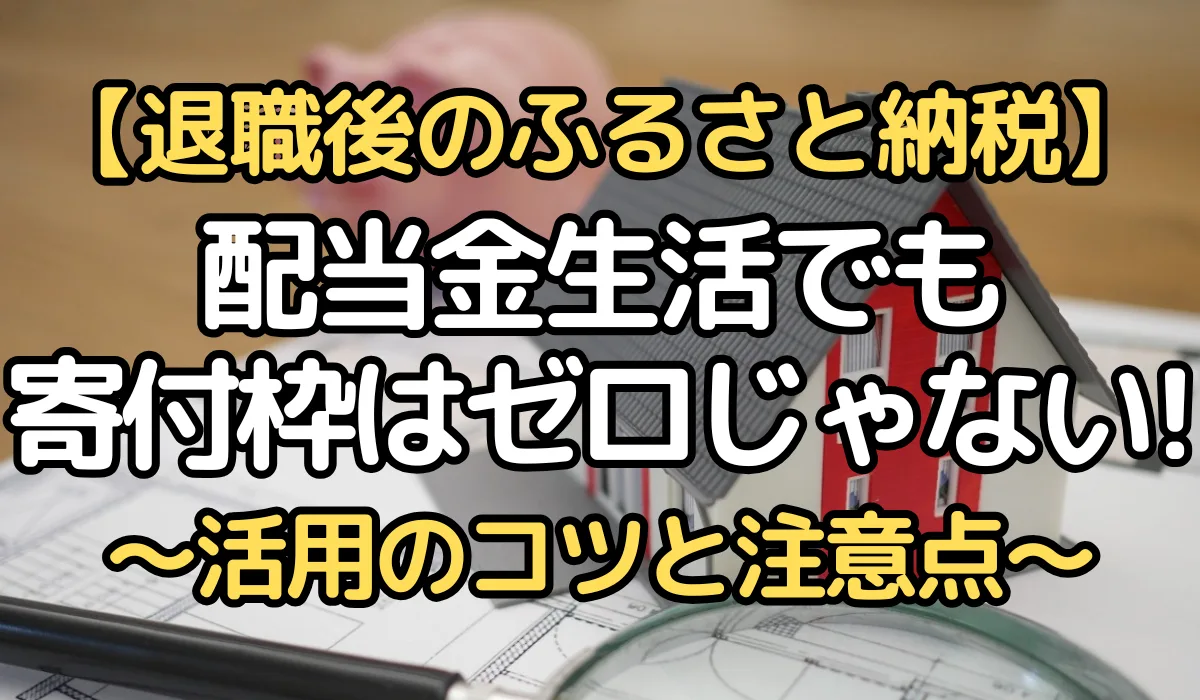
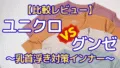
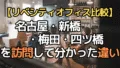
コメント